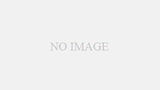財政状態や経営成績など事業の結果(過去)を示す決算書。
金融機関にとっては、それが過去だけではなく未来を読むための資料にもなります。
よって、決算書を金融機関に提出する際には、ただ提出するだけではなく、決算書の内容をどう説明するかが重要となります。
説明で増す数字の説得力
金融機関が融資を検討するとき、数字そのものも見ますが、それ以上に重要視しているのが数字の背景です。
たとえば、「売上が〇億円あります」と言うだけよりも「売上が前年より〇%増えた背景には、〇〇したことが寄与しています」と説明すれば、戦略性や再現性が伝わります。
その数字がどうやって生まれたのか、何が良くて何が悪かったのか、それに対してどんな打ち手を考えているのか。
こういった説明を行うことで数字の印象が大きく変わります。
決算書を説明書に変える3つの視点
数字の説得力を増すために、つぎの3つの視点を意識してみましょう。
・過去と比較する
決算書は単年の数字だけを見ても良し悪しの判断がつきにくいので、過去と比較して分析してみましょう。
たとえば、「前期と比べてどう変わったか」について、自分の言葉で数字の変化とその理由をセットで説明できれば数字の説得力が増します。
・業界と比較する
経常利益率が5%でも、「業種別平均が2%の中で5%」と「業種別平均が10%の中で5%」なら捉え方が異なります。
インターネットで「業種別平均 経営指標」などと検索すれば、参考になる数値を見つけることも可能です。
自社の数字に「業界との比較」という視点を加えることで、会社の立ち位置などがより伝わりやすくなります。
・見通しを加える
決算書は過去の結果ですが、金融機関が見たいのは未来の見通しです。
決算書の内容を説明する際には、「今期は赤字だったが来期は〇〇を行うことにより黒字化を見込んでいる」など今後どうなるかを説明することも必要です。
まとめ
- 決算書は「提出する書類」ではなく「説明する資料」
- 金融機関は、数字そのものに加え、その背景や経営者の理解度も見ている
- 決算書は比較して分析し、今後の見通しを説明することが重要