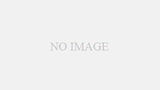金融機関との信頼関係を築くうえで大きな武器となる事業計画書。
金融機関との面談では、過去の実績だけでなく、これからの展望も重視されます。
そして、その未来のビジョンを伝えるツールが事業計画書です。
金融機関から見た事業計画書とは
金融機関は、「この会社に融資して大丈夫か?」という視点で事業を見ています。
その判断の材料になるのが、過去の決算書と未来の事業計画書なわけですが、
では、どんな事業計画書が評価されるのか?
それには次の要素が不可欠です。
・資金の使い道が明確であること
融資した資金を「何のために使うのか」が曖昧では、金融機関は不安になります。
機械の入れ替え・新店舗のオープン・売上拡大に伴う運転資金など、具体的な用途を明記することが大切です。
・返済計画が現実的であること
融資を受けた資金を「どう返していくか」が明示されていないと、金融機関は判断に困ります。売上が伸びても、キャッシュが残らなければ返済はできません。
そのため、キャッシュフローに基づく返済スケジュールを盛り込むことが重要です。
・実現可能な数字で構成されていること
「売上を2倍にします!」と言われても、根拠がなければ単なる願望に聞こえます。
数字には必ず裏付けが必要です。
数字の根拠が信用をつくる
事業計画書の中で、次のような数字のロジックが組まれていると説得力が高まります。
・効果
「新しい冷蔵機材の導入により、製造キャパが1.5倍になる」、「新規取引先の獲得で月間売上が20万円増える」といったように、投資と効果の因果関係を説明しましょう。
・売上根拠
「客数×客単価」など、まずはシンプルな式でもかまいません。
たとえば、「新たにECサイトを開設し、月100件の注文、平均単価5,000円を見込む」といった感じです。さらに、「既存顧客のリピート率を20%改善する」など、具体的な施策と数字がセットになっていると説得力が増します。
・返済原資
「当期純利益100万円に減価償却費50万円を加えた簡易キャッシュフローは150万円であり、返済額100万円に対して余力あり」といったように、簡易キャッシュフロー(当期純利益+減価償却費)が返済額を上回ることを示します。
まとめ
- 金融機関は過去だけでなく未来も重視している
- 事業計画書には資金使途、返済計画、数字の根拠が必要
- 数字で語れる社長は銀行との関係が長続きする