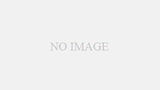決算書は会社の経営成績や財政状態を示す重要な書類です。
銀行は決算書を「この会社に安心してお金を貸せるか」の判断材料のひとつとしますが、一部の数字が「怪しい」と感じられると、一気に信頼を損ねてしまうおそれがあります。
銀行が警戒する4つの数字
銀行の担当者は、日々たくさんの決算書を見ています。
その中で「これはちょっとおかしいな…」と目を留める、代表的な4つの疑われがちな数字を紹介します。
① 売上が急激に増えている(特に期末だけ)
たとえば、3月決算の会社が、1〜2月までは前年並みの売上だったのに、3月だけ売上がドンと跳ね上がっているケース。
これは「決算対策で無理やり売上を計上したのでは?」と疑われます。
いわゆる「駆け込み売上」や「架空売上」のような印象を与えてしまいかねません。
② 棚卸資産が急に増えている
売れていない在庫を多く抱えているのに、無理に資産として評価して帳簿に残しているケース。
「実は不良在庫なのに、売れることにして利益を確保していないか?」と見られます。
棚卸資産の急増は、利益操作の疑いをもたれやすいポイントです。
③ 役員貸付金や仮払金が異常に大きい
社長個人が会社からお金を借りていたり(役員貸付金)、使途不明な支出が処理されていたり(仮払金)するケース。
「会社の資金が私的に流用されているのでは?」と非常に悪い印象を持たれます。
④ 減価償却費がゼロ、または不自然に少ない
減価償却は固定資産の価値が時間とともに減っていくことを会計的に表す処理です。
これがゼロだったり、不自然に少なかったりすると、「本当はもっと経費を計上すべきなのに、利益を大きく見せようとしているのでは?」と不信感を持たれます。
特に利益を黒字にするために償却費を意図的に減らすケースは、銀行側の信用を大きく失います。
正直な決算書が信頼を生む
会社の業績は、いつも右肩上がりとは限りません。
売上が下がった年、利益が出なかった年があって当然です。
大切なのは、無理にキレイに見せようとしないこと。
少し数字が悪くても、きちんと「なぜこうなったか?」、「今後どう改善していくか?」を説明できれば、理解を得やすくなります。
逆に、数字を調整して見栄えを良くしようとした結果、不自然な数値が出てしまうと、「この会社は何か隠しているかもしれない」とかえって疑いを招きます。
銀行が見ているのは「数字」そのものだけでなく、その背後にある社長の姿勢や誠実さです。
言い換えれば、「信頼できる社長かどうか」が判断基準なのです。
まとめ
- 銀行は決算書の裏側にある経営の実態や姿勢を見ようとしている
- 減価償却ゼロなど怪しまれやすい数字は特に注意
- 正直な決算と丁寧な説明が長期的な信頼を生む